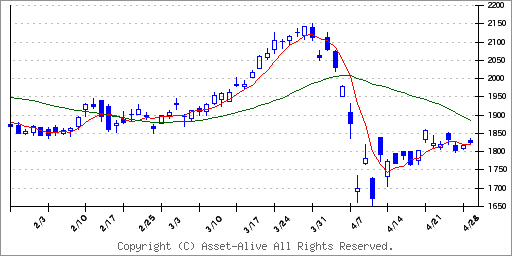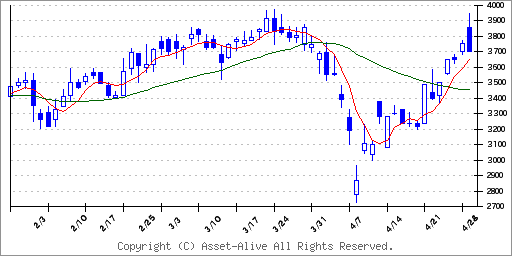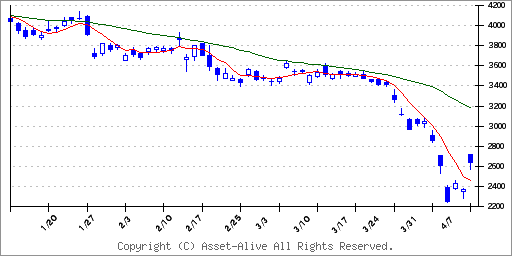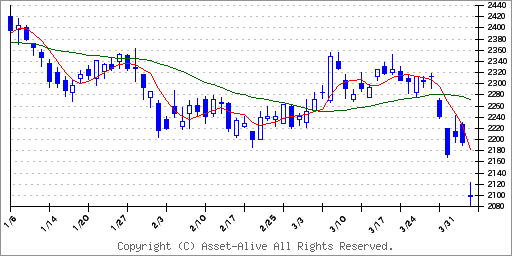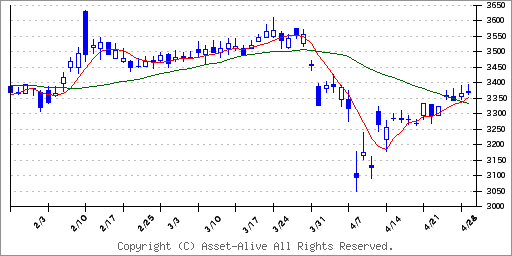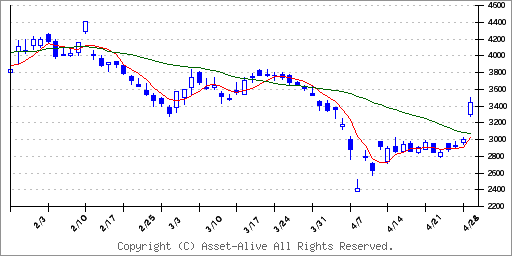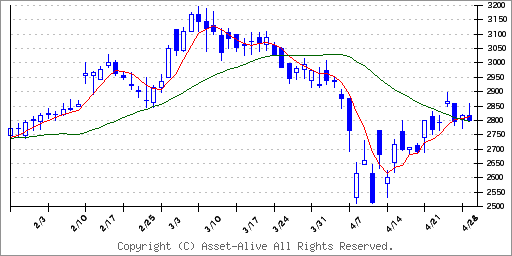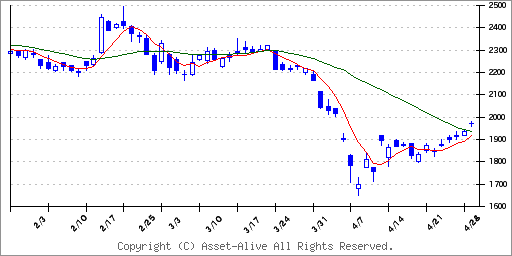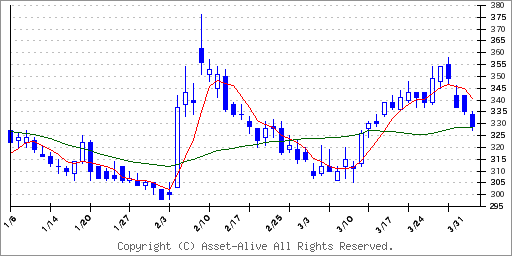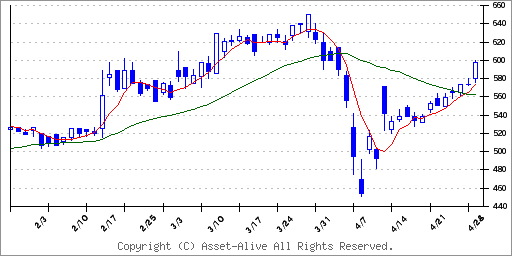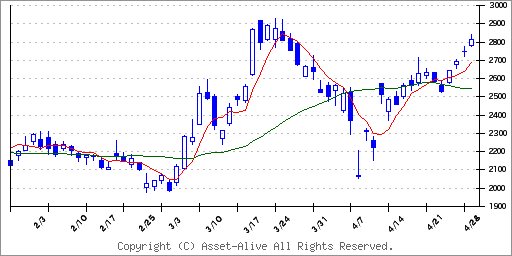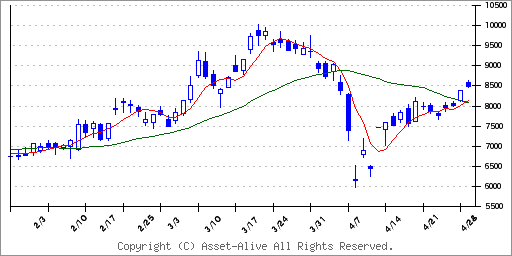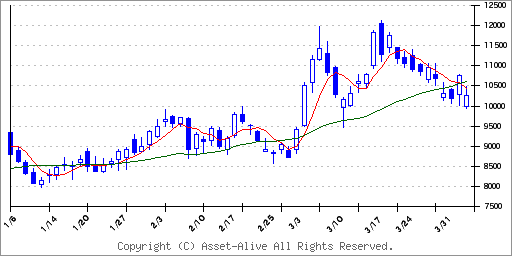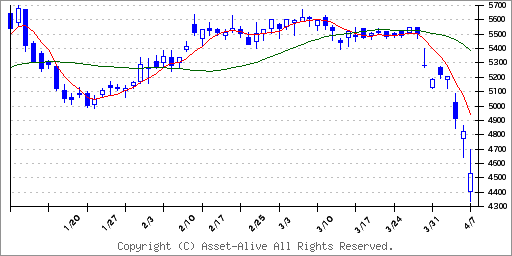株テーマ:アンモニアの関連銘柄
アンモニア関連株。アンモニアは燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出しないクリーンエネルギーとされる。アンモニアと石炭を混ぜて発電に使い技術の実用化も進められており、石炭火力のCO2排出量の削減が期待される。政府は2030年に300万トン、2050年に3000万トンを導入する目標を掲げる。
・5463丸一鋼管
水素やアンモニアを運ぶインフラ需要が見込まれるステンレスシームレス鋼管や配管用ステンレス溶接管への設備投資を実施。投資額は260億円で、稼働は2027年以降を予定する。
・6016ジャパンエンジンコーポレーション
ジャパンエンジンコーポレーションなど4社は、2022年9月に研究開発中のアンモニア燃料アンモニア輸送船について、一般社団法人日本海事協会から基本設計承認を取得。2026年度の実証運航実現に不可欠となる代替設計承認を見据える。
・6363酉島製作所
燃料アンモニア用ポンプの開発では2027年の商用化に向けて開発を推進。
・1964中外炉工業
2026年度をめどに都市ガスに代わり、アンモニアを燃料とする工業炉を実用化するもよう。大阪大学と本来は燃えにくいアンモニアと空気を混ぜて、効率よく燃焼する技術を開発。国内CO2排出量の6%を占める工業炉の環境負荷を抑える。
・6333帝国電機製作所
アンモニア燃料船や石炭火力アンモニア混焼向けなどのポンプを開発。2030年までの実用化を目指す。
・7013IHI
燃料アンモニアバリューチェーンの社会実装が2028年度から本格化する見通し。
・6366千代田化工建設
NEDOのグリーンイノベーション基金事業として、製造コストの低減を実現する新規アンモニア合成技術の開発を進める。また、JERA、日本触媒と共同でアンモニア分解技術の開発を進める。
・4012川崎重工
エネルギーソリューション&マリンセグメントでLPG/アンモニア運搬船を展開する。
・7011三菱重工
2022年にシンガポールでのアンモニアバンカリングプロジェクト実現に向けた覚書を締結。2024年~2026年の事業計画期間においてはこのプロジェクトの具体化を図る。
・6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
2024年4月に推進しているアンモニア燃焼技術開発で、アンモニアなど燃焼し難い燃料を安定燃焼させることが可能な超高エネルギー点火システムの試作品を開発。
・9104商船三井
カーボンソリューション専門部署を発足し、アンモニア・水素・CO2関連の事業化を推進。