9984 ソフトバンクグループ
| 2026年2月19日 株価 | |||
|---|---|---|---|
|
始値
4,356円
|
高値
4,555円
|
安値
4,291円
|
終値
4,440円
|
|
出来高
53,224,200株
|
|||
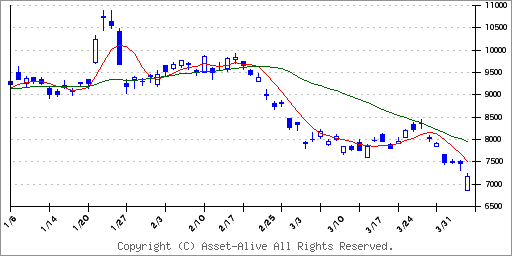
| オシレータ分析 | トレンド分析 | 予想レンジ | |
|---|---|---|---|
 |
 |
予想高値
4,800円
|
予想安値
4,000円
|
-
- AI半導体
- AIエージェント
- フィジカルAI
- コネクテッドカー
- 競馬
- 野球
- アーム
- クアルコム
- マイクロソフト
- TOPIXコア30
- 対米投資
- 空き駐車場シェア
- シェアオフィス
- 自動運転トラック
- 2017年
- 2026年有望銘柄
- スーパーアプリ注目株
- 電子書籍(マンガアプリ)
- 日本版マグニフィセント・セブン
- ムーンライト
- 大規模太陽光発電所(メガソーラー)
- スターゲート計画
- がんゲノム医療
- インテル
- データレンディング
- 風力発電事業者
- MaaS
- モネ・テクノロジー
- 日本デジタル空間経済連盟
- 量子コンピュータ
- コミュニケーションロボット
- サービスロボット
- 清掃ロボット
- 人型ロボット(ヒューマノイド)
| みんなの予想 | |||
|---|---|---|---|
| 上がる 71.4% |
下がる 28.6% |
平均予想株価 4,682円 |
|
この銘柄の株価は |
|||
オシレータ分析

オシレータ系指標は、相場の強弱動向を表した指標で、日々の市場の値動きから、株価の水準とは無関係に売り・買いを探ります。
売買シグナルは 内にまたはで表示されます。
| RSI | 9日 62.54 | RCI |
9日 21.67 13日 63.19 |
|---|---|---|---|
| ボリンジャーバンド |
+2σ 4797.01 -2σ 3842.22 |
ストキャススロー |
S%D 67.44 %D 69.01 |
| ストキャスファースト |
%K 53.91 %D 69.01 |
ボリュームレシオ | 14日 53.46 |
| 移動平均乖離率 | 25日 4.94 | サイコロジカル | 12日 58.33 |
トレンド分析

トレンド系指標は、相場の方向性・強さを判断する指標で、中長期の分析・予測に使われます。トレンド転換時は内にまたはで表示されます。現在のトレンドはまたはで表示されます。
| DMI | MACD | ゴールデンクロス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5日移動平均(位置) | 5日移動平均(向き) | 25日移動平均(位置) | |||
| 25日移動平均(向き) | パラボリック |
チャート分析

酒田五法や一目均衡表などローソク足変化シグナル(当日示現のみ)は、内にまたはで表示されます。独自のHAL指数で高値圏、安値圏を判定し、実戦的なシグナルです。
| 十字足 | はらみ十字 | 上ひげ・下ひげ |
|---|---|---|
| 出会い線 | 三点童子 | 三点童子(安値・高値) |
| 包み足 | 赤三兵・黒三兵 | 並び赤・並び黒 |
| 明けの明星・宵の明星 | 三役好転・三役逆転 | 雲上抜け・下抜け |
| 転換線上抜け・下抜け | 遅行線上抜け・下抜け | 五陽連・五陰連 |

9984 ソフトバンクグループの投資戦略
9984 ソフトバンクグループの株価は、オシレーター系指標では中立圏で推移しています。トレンド系指標は上昇トレンド継続中で、押し目買いゾーンです。オシレータ系指標は「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」を示すテクニカル指標の総称です。一定の範囲で動くため振り子系指標とも呼ばれます。RSIやストキャスティクスが代表的です。トレンドフォロー系指標は、株価が上がり続けると指標も上がり、下がり続けると指標も下がるタイプです。移動平均やMACDが代表的です。
9984 ソフトバンクグループのテクニカル売買シグナル
株式売買シグナルが点灯しています。このページ下部のオシレーター分析、トレンド分析、チャート分析でご確認ください。オシレーター分析、チャート分析では変化点をキャッチした日に売り買いサインが点灯、トレンド分析では現在の方向を矢印で示します。
9984 ソフトバンクグループの関連ニュース
PayPayは国内QR決済で圧倒的なシェアを持ち、利用者基盤を拡大してきた。足元では米クレジットカード大手ビザとの提携を発表し、決済ネットワークの国際接続を強化する。米国を起点に海外展開を本格化させる戦略であり、成長ストーリーを明確に打ち出した形だ。
市場では、国内中心の決済事業からグローバル金融プラットフォームへの転換が評価材料になるとの見方が出ている。一方で、米国市場での競争は激しく、規制対応や収益モデルの確立が課題となる可能性もある。想定時価総額3兆円超が維持されるかどうかは、上場後の成長期待と業績進展次第だ。
(9984)ソフトバンクグループの直近決算では、投資事業の変動が業績を左右する構図が続いている。PayPay上場は保有資産の価値顕在化につながり、純資産の押し上げ要因となる。売却比率を抑える姿勢からは、中長期的な企業価値拡大を狙う意図がうかがえる。
AIや半導体投資に加え、フィンテックの柱を世界市場へ広げる今回の上場は、ソフトバンクグループのポートフォリオ再構築の一環だ。市場は、上場後の株価動向と、グローバル展開の実効性を注視する局面に入る。
増益の主因は投資損益である。9カ月累計の投資損益は4兆2,203億円と前年同期比で約2兆503億円増加した。特にSVF事業の投資益が3兆5,952億円と大幅に拡大し、前期の評価損局面から一転した。一方、持株会社投資事業の投資益は1,633億円にとどまり、前年同期の2兆84億円から大きく減少した。
セグメント別では、ソフトバンク事業は売上高5兆1,960億円、セグメント利益8,468億円と増益を確保した。コンシューマ、エンタープライズ、ファイナンス事業の伸長が寄与している。またAIコンピューティング事業ではArmを中心とした半導体関連が売上拡大を続けている。
財務面では資産合計55兆5,573億円、親会社所有者帰属持分は15兆6,386億円、自己資本比率は28.1%へ改善した。包括利益は4兆8,046億円に達している。
なお、通期業績予想は非開示である。業績は投資損益の変動に大きく左右される構造が続く。今回の決算は、SVF評価益の回復とデリバティブ関連損益の改善が重なり、再び巨額黒字を計上した点が核心である。生成AI関連銘柄や半導体投資の回復が、グループ収益を押し上げた形だ。
ソフトバンクグループはOpenAIに対し巨額の出資を行っており、生成AI分野における戦略投資の象徴的存在だ。これまで同社株は、ビジョン・ファンドの評価損や金利環境の変化を背景にディスカウント評価が続いてきたが、OpenAIの企業価値が再び切り上がれば、純資産価値(NAV)全体の見直しにつながるとの見方が強まっている。市場では「非上場であるがゆえに織り込まれてこなかった価値が、ようやく株価に反映され始めた」との解釈が広がる。
テクニカル面でも変化は明確だ。株価は25日移動平均線を上抜け、出来高を伴って上昇している。直近では4,300円台でのもみ合いを上放れ、短期的な戻り高値を更新した。RSIは過熱感の手前で推移しており、トレンド転換初動と評価する向きが多い。次の上値メドとしては、75日線が意識されやすい局面だ。
もっとも、OpenAI関連の評価は依然として報道ベースの期待先行であり、資金調達条件や上場時期次第では変動要因となる。短期的にはテーマ性と需給が株価を押し上げている段階で、中長期では投資先の価値実現がどこまで進むかが焦点となる。市場は今、ソフトバンクグループを「AI純度の高い投資会社」として再定義し始めている。
市場では、OpenAIの企業価値拡大が実現すれば、ソフトバンクグループの純資産価値(NAV)押し上げ要因になるとの見方が広がっている。特に、未上場AI企業への投資比率が高い同社にとって、外部資金の流入と高水準のバリュエーションは、保有株式の含み価値を顕在化させる材料となりやすい。
加えて、生成AI分野への投資マネーが引き続き中東の政府系ファンドなど長期志向の資金から流入している点も、安心感につながった。AIインフラ投資や計算資源拡充を巡る競争が激化する中で、ソフトバンクグループがAIエコシステムの中核に位置付けられているとの評価が、株価を下支えした格好だ。
既に完了した投資と出資状況
2025年12月末時点でソフトバンクはOpenAIへの大規模出資を完了しており、約410億ドル規模の資金供給を通じて**同社持分は約11%**になったと公式発表された。これは2025年3月にコミットした追加出資のファースト(75億ドル)とセカンド(225億ドル)、外部投資家シンジケーション分を含むものである。
2025年の投資ラウンドは最大400億ドル規模で、当初OpenAIの評価額は約3000億ドルだったが、その後ビジネス進展と二次株式売却等の結果、評価額は約5000億ドルへと拡大したとの報道もある。
(9984)ソフトバンクグループは、OpenAIが9日、同社傘下の米発電会社SB Energyに5億ドルを出資すると発表した。ソフトバンクグループも同額の5億ドルを追加出資し、SBエナジーの資本基盤を大幅に強化する。オープンAIとSBGは、AI向けデータセンターを共同で開発・運営する体制を構築する。
今回の取り組みは、オープンAIとソフトバンクグループが推進する総額5000億ドル規模の米国AIインフラ整備構想「スターゲート」の一環だ。SBエナジーは同計画において、オープンAIが使用するデータセンターの建設・運営に加え、安定的な電力供給を担う中核的な役割を果たす。増資により、大規模設備投資を伴う事業拡大が可能となる。
具体策として、オープンAIはSBエナジーが米南部テキサス州ミラム郡に建設するデータセンターをリースで借りる契約を締結した。電力容量は1.2ギガワットと、原子力発電所1基分に相当する超大型施設で、2026年内から段階的に稼働を始める計画だ。同拠点では、発電施設の併設も予定されており、電力供給の安定性とコスト競争力を両立させる狙いがある。
SBエナジーは、太陽光発電や蓄電事業を主力とするソフトバンクグループの米子会社で、近年はデータセンターの建設・運営分野へ事業領域を広げている。株主にはSBGのほか、米投資ファンド大手のAres Managementも名を連ね、同社も今回新たに8億ドルを追加拠出した。
AI需要の拡大に伴い、演算能力だけでなく電力とインフラの確保が競争力を左右する局面に入っている。ソフトバンクグループは、AI開発から電力・施設までを一体で押さえる戦略を鮮明にし、スターゲート構想の実現性を高めつつある。今後は、巨額投資が収益化に結びつくかが株価評価の焦点となりそうだ。
技術面では、企業ごとに専用のAIエージェントを構築し、社内文書、基幹システム、CRM、財務データなどを安全に接続。過去データを蓄積する長期記憶機構を備え、継続的に学習しながら高度化する構造を想定する。これにより、単発の質問応答にとどまらず、業務の文脈を理解した判断支援やタスク実行が可能になる。
企業向けユースケースとしては、第一に業務プロセスの自動化が挙げられる。経理・人事・法務などで発生する定型業務をAIが代行し、資料作成や社内報告の自動生成を実現する。第二にデータ分析と意思決定支援だ。売上や在庫、顧客行動といった分散データを横断的に解析し、需要予測や異常検知、経営指標のリアルタイム提示を可能にする。第三に営業・顧客対応支援で、顧客属性や過去履歴を踏まえた提案文面の生成や問い合わせ対応の自動化により、フロント業務の生産性向上が期待される。
さらに、社内ナレッジの統合も重要な用途だ。会議議事録やプロジェクト資料を一元管理し、必要な情報を即座に検索・要約することで、属人化しがちな知識の共有を促進する。
ソフトバンクグループはまず自社グループ内で大規模導入を進め、運用実績を外販に展開する方針だ。労働人口減少と業務高度化が同時進行する日本企業にとって、クリスタル・インテリジェンスはDXを次の段階へ押し上げる基盤として注目される存在になりそうだ。
デジタルブリッジは、データセンター、通信鉄塔、光ファイバー、スモールセルなどデジタルインフラを中核とする実物資産投資を得意とする。特に通信鉄塔分野では、日本のJTOWER、ドイツのGD Towers Holding、ベルギーのBelgium Tower Partners、米国のVertical Bridge REITなどをポートフォリオに持ち、グローバルに分散した通信資産を保有する点が強みだ。
ソフトバンクグループはAIの計算需要拡大を背景に、半導体、データセンター、通信網を一体で押さえる戦略を鮮明にしている。今回の買収により、AIデータセンター建設やエッジ拠点整備を迅速に進める土台を確保した格好だ。投資会社という立ち位置を通じ、需給変動の大きいAIインフラ分野でも柔軟な資本配分が可能になる。
一方、短期的には買収負担や投資回収期間の長期化が意識されやすい。ただ、市場ではAIインフラは中長期で高い成長が見込まれており、既存の投資先ネットワークを活用できるデジタルブリッジの組み込みは合理的と受け止められている。ソフトバンクグループは、AI時代の基盤インフラを握ることで、次の成長局面への布石を打ったと言えそうだ。
孫正義CEOにとって、オープンAIへの「全面的な」投資は、これまでで最大規模の賭けとなる。生成AIを巡る競争が激化する中、同社は中核となるAIプラットフォームへの関与を一段と深め、自社の戦略的ポジションを強化する狙いだ。
資金確保のため、ソフトバンクグループはすでにAI半導体大手のNVIDIA株約58億ドル相当を全て売却したほか、米通信大手のT-Mobile US株も約48億ドル分を売却した。加えて人員削減など、グループ全体で資金効率を重視した動きが進んでいる。
こうした中、孫氏はソフトバンク・ビジョン・ファンドにおける新規投資を抑制しており、5000万ドル超の案件については自身の明確な承認が必要となった。市場では、投資資源をオープンAIに集中させる姿勢が鮮明になったとの見方が広がっている。
一方、同社は決済アプリを手がけるPayPayの新規株式公開も準備している。IPOは来年第1四半期が視野に入っており、実現すれば200億ドル超の資金調達が見込まれる。オープンAIへの巨額投資と資金調達策の進展が、今後の株価評価を左右する局面となりそうだ。
ソフトバンクグループは傘下のソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じ、未上場のオープンAIに出資している。今回の大型調達観測は、同社が保有する未公開資産の価値再評価につながるとの見方が市場で広がり、株価の押し上げ要因となった。資金調達ラウンドは初期段階にあり、早ければ来年第1四半期末までの完了を目指しているとされる。
市場では、生成AIを中核としたプラットフォーム価値の拡大が、ビジョン・ファンドの含み価値を大きく左右するとの見方が根強い。オープンAIはAI基盤モデルの高度化に加え、法人向けサービスやエコシステム形成を進めており、評価額の上振れ余地が意識されやすい局面だ。
この工場改修は、同社が米国において展開を進めている「スターゲート」と呼ばれるAIインフラ構築計画の一環と位置付けられる。スターゲートは、米国の中西部および南部に複数のデータセンターを設置し、AI/高性能コンピューティング用途の大規模設備を展開するプロジェクトで、ソフトバンクグループ、OpenAI、Oracle Corporationが関与している。
当初、このオハイオ拠点には小規模なデータセンター建設が予定されていたが、ソフトバンクグループのCFOである後藤芳光氏は決算説明会にて「高性能コンピューティングの需要に対応するため、AIインフラ向けの機器・装置の製造に特化していく」と説明していた。この方向転換により工場は、モジュール型データセンター向けユニットの製造を担い、南部テキサス州ミラム郡など他のデータセンター向けにもユニットを出荷する計画という。
報道では、同工場の製造稼働開始時期は2026年第1四半期(1~3月)になる見込みだという。モジュール型ユニットとは、あらかじめ製造された標準モジュールをデータセンターに搬入・設置する手法で、敷地造成や建築を待たずに迅速に稼働できる強みを持つ。
この動きの背景には、生成AIや大規模言語モデル、AIクラスタ構築の急速な拡張がある。データセンター建設の競争激化、電力・冷却・通信インフラの確保難、グローバル製造サプライチェーンの再構築など、AIインフラを巡る構造変化が浮き彫りになっており、ソフトバンクグループは製造拠点の確保を“外部調達”から“自社製造・モジュール展開”へとシフトしつつある。
財務面では、この種の巨額投資がグループの財務的余力やキャッシュフロー、借入リスク管理にどのように影響を及ぼすかが注目される。CFOはレバレッジ比率を25%水準に抑える方針を改めて示しており、リスク制御を意識した姿勢を示している。
この工場改修は、同社が米国において展開を進めている「スターゲート」と呼ばれるAIインフラ構築計画の一環と位置付けられる。スターゲートは、米国の中西部および南部に複数のデータセンターを設置し、AI/高性能コンピューティング用途の大規模設備を展開するプロジェクトで、ソフトバンクグループ、OpenAI、Oracle Corporationが関与している。
当初、このオハイオ拠点には小規模なデータセンター建設が予定されていたが、ソフトバンクグループのCFOである後藤芳光氏は決算説明会にて「高性能コンピューティングの需要に対応するため、AIインフラ向けの機器・装置の製造に特化していく」と説明していた。この方向転換により工場は、モジュール型データセンター向けユニットの製造を担い、南部テキサス州ミラム郡など他のデータセンター向けにもユニットを出荷する計画という。
報道では、同工場の製造稼働開始時期は2026年第1四半期(1~3月)になる見込みだという。モジュール型ユニットとは、あらかじめ製造された標準モジュールをデータセンターに搬入・設置する手法で、敷地造成や建築を待たずに迅速に稼働できる強みを持つ。
この動きの背景には、生成AIや大規模言語モデル、AIクラスタ構築の急速な拡張がある。データセンター建設の競争激化、電力・冷却・通信インフラの確保難、グローバル製造サプライチェーンの再構築など、AIインフラを巡る構造変化が浮き彫りになっており、ソフトバンクグループは製造拠点の確保を“外部調達”から“自社製造・モジュール展開”へとシフトしつつある。
財務面では、この種の巨額投資がグループの財務的余力やキャッシュフロー、借入リスク管理にどのように影響を及ぼすかが注目される。CFOはレバレッジ比率を25%水準に抑える方針を改めて示しており、リスク制御を意識した姿勢を示している。
投資事業のうち、ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)事業の投資損益は3兆4154億円と約5倍に拡大。生成AI(人工知能)関連投資や保有株の評価益が利益を押し上げた。一方、持株会社投資事業の投資損益はアリババやTモバイル株の評価損を計上し、3639億円と前年から大きく減少した。
財務面では有利子負債の削減と自己株式取得が進み、資本合計は前期末比で2兆9000億円増の16兆8600億円。自己株買いは当期中に総額932億円、翌10月末に4203万株を消却した。
配当は中間で1株22円を実施済み。12月末を基準日に1株を4株に分割し、個人投資家の参入促進を図る。キャッシュフローでは営業活動による収支がマイナス1199億円と前年から悪化したが、投資活動では売却益が膨らみ、全体では現金残高が4980億円に増加した。
通期見通しについては「不確定要素が多く、業績予想の公表を控える」としており、AI・半導体関連の市況動向が今後の収益を左右する見通しだ。
投資事業のうち、ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)事業の投資損益は3兆4154億円と約5倍に拡大。生成AI(人工知能)関連投資や保有株の評価益が利益を押し上げた。一方、持株会社投資事業の投資損益はアリババやTモバイル株の評価損を計上し、3639億円と前年から大きく減少した。
財務面では有利子負債の削減と自己株式取得が進み、資本合計は前期末比で2兆9000億円増の16兆8600億円。自己株買いは当期中に総額932億円、翌10月末に4203万株を消却した。
配当は中間で1株22円を実施済み。12月末を基準日に1株を4株に分割し、個人投資家の参入促進を図る。キャッシュフローでは営業活動による収支がマイナス1199億円と前年から悪化したが、投資活動では売却益が膨らみ、全体では現金残高が4980億円に増加した。
通期見通しについては「不確定要素が多く、業績予想の公表を控える」としており、AI・半導体関連の市況動向が今後の収益を左右する見通しだ。
同社株は10日時点で終値2万2255円と、年初来安値5835円から約4倍に上昇。投資単位が200万円を超えており、個人投資家を中心に売買単位を下げる要望が強まっていた。株式分割を通じ、投資家層の拡大を狙う。
資本金の変更はなく、新株予約権の行使価額も比例調整する。また、定款の一部を改定し、発行可能株式数の倍増に対応する。配当については、26年3月期の期末予想を分割後の株式数に合わせて修正する。従来22円としていた期末配当は、分割後換算で5円50銭となるが、実質的な配当水準の変更はない。
直近では生成AI事業への積極投資や、オープンAIとの新会社設立などが注目を集めており、株価上昇を背景に流動性確保の観点からも分割は市場に好感される可能性が高い。
1株を4株に分割することで実質的な投資単位が引き下げられ、流動性と個人投資家の参加拡大が見込まれる。AI関連投資による成長期待も高く、株式分割後も中長期での上昇余地は大きいとみられる。
ソフトバンクは2025年3月、OpenAIに数十億ドル規模の出資を行ったとされる。報道によれば、当時のOpenAIの評価額は約3,000億ドル(約42兆円)であり、ソフトバンクは同ラウンドの中心投資家だった。出資比率は公表されていないが、市場では数%規模(1〜3%程度)との推定が多い。現在、OpenAIの評価額は5,000億ドル(約75兆円)へ上昇しており、仮にソフトバンクの持分が2%なら評価額は約100億ドル(約1.5兆円)に達する計算となる。
OpenAIのIPOが成功し、時価総額が想定レンジ上限の1兆ドル(約150兆円)に達すれば、ソフトバンクの保有株式価値は最大200億ドル(約3兆円)規模まで拡大する見通しだ。これは、同社がかつて中国アリババ株で得た莫大なキャピタルゲインに次ぐ「第二のアリババ効果」として市場が注目する構図である。
資本面での恩恵に加え、OpenAIとの連携による戦略的波及効果も見逃せない。ソフトバンクは国内通信事業や孫正義会長主導の「AI群戦略」において、生成AIの応用領域(教育、物流、金融、自治体業務など)を拡大中だ。OpenAIが上場により資金調達力を高め、AIモデルやインフラ開発を加速させれば、ソフトバンク傘下の企業群(SBテクノロジー、アーム、LINEヤフーなど)に技術・事業シナジーが波及する可能性が高い。
さらに、OpenAIがマイクロソフトやエヌビディアに並ぶ世界的AIプラットフォーマーとして地位を確立すれば、ソフトバンクのAI投資戦略全体の信頼性向上にも寄与する。孫会長が提唱する「AIインフラ時代への備え」を象徴する投資案件となり、同社のNAV(純資産価値)評価にも上方圧力がかかる見通しだ。
一方で、リスク要因としては、IPO時の評価倍率が過熱した場合の反動や、出資比率が少数にとどまることによる影響力の限定性が挙げられる。OpenAIの経営は非営利母体が監督する公益法人構造のため、ソフトバンクが経営権や意思決定に直接関与する余地は限られる。それでも、IPOによる評価顕在化は、同社のポートフォリオの含み益拡大につながる公算が大きい。
総じて、OpenAIのIPOが順調に進めば、ソフトバンクは財務・象徴・戦略の三つの軸で恩恵を受ける。特に、AI領域での資産再評価は市場心理を刺激し、同社株に再び「AI関連の本命」というテーマ性を与える可能性がある。
評価:強気(Buy)
OpenAI上場成功により、ソフトバンクのAI関連資産価値が顕在化する可能性が高い。IPO後のOpenAI評価が1兆ドル水準となれば、同社のNAVは2兆〜3兆円規模押し上げられる見通し。短期的には話題先行だが、中期的にはAI群戦略の核心銘柄として再評価が進む局面だ。
マイクロソフト主導の体制強化は、世界的な生成AI投資熱を再び高める契機となる。これにより、SBG傘下のArm(アーム)や出資先のAnthropic(アンソロピック)など、AI関連銘柄の再評価が進む公算が大きい。特にArmはAIチップ設計で世界シェアの9割を握り、生成AI需要の急拡大によるデータセンター投資増加の恩恵を受ける。オープンAIが高性能AIモデルを開発・提供するほど、Armの省電力CPUやAIアクセラレーター採用が進むとの見方が市場で広がる。
また、SBGが推進する「Stargate計画」(AIデータセンター網構想)にも追い風となる。生成AIの処理需要は急増しており、電力供給・半導体・通信網の総合整備が不可欠となる。今回の再編は、AIインフラ構築への世界的な投資競争を加速させ、SBGが構想する超大規模データセンター構築に正当性を与える形だ。
財務面では、Armの株価上昇に伴い保有資産価値(NAV)の改善が期待できる。SBGは9月末時点でArm株を約90%保有しており、同社の時価上昇は連結純資産の押し上げ要因になる。AI関連への再評価が進めば、SBGの投資ポートフォリオ全体の含み益拡大が見込まれる。
市場では「マイクロソフト主導のAI市場拡大は、Arm・Anthropic・Stargateを抱えるSBGにとって最も理想的な環境を再びつくり出す」との声が多い。短期的な資金流出懸念よりも、AIインフラの本格拡大による資産価値上昇が勝るとみられる。
マイクロソフトによるオープンAI再編は、AI関連資産の再評価を誘発するポジティブ要因。SBGはArmを通じてAIハード基盤を、Anthropicを通じてAIソフト基盤を押さえており、世界的なAI投資ブームの再拡大局面で最大の受益者候補となる。短期の株価変動に左右されず、中長期でのAI資産価値の再上昇を見込んで買い判断とする。
また、米Stack AVはトラック向け自動運転システムを開発しており、ソフトバンクが単独で出資。商用物流分野での自動化需要を見据えた投資とみられる。さらに、かつてはGM傘下のCruiseやNuroなどにも出資しており、同グループのVision Fundを通じて一貫して自動運転エコシステムを形成してきた。
国内では、子会社BOLDLYを軸に自動運転バスや遠隔監視システムの実証を推進。トヨタなどと共同出資するMONET Technologiesを通じ、移動サービスの社会実装にも踏み出している。通信インフラやAIプラットフォーム事業と連動する形で、今後は都市交通・物流・公共インフラ分野での事業展開を拡大する構えだ。
世界的に自動運転開発は淘汰局面にあるが、ソフトバンクはAI基盤を武器に次世代モビリティ市場を先導する姿勢を明確にしている。
ウェイブは2017年に創業し、AIによる「エンド・ツー・エンド」型の自動運転技術を開発する新興企業だ。車載カメラとセンサーで取得した映像データを基に、深層学習によって走行判断を行う方式を採用している。現在は英国と米国を中心に事業を展開しており、ドイツや日本市場でも試験・開発業務を拡大中だ。
ソフトバンクは2023年にもウェイブの資金調達を主導し、AIチップ大手エヌビディアも支援に参加した。米配車大手ウーバーも2024年に非公開で出資しており、AI自動運転の次世代基盤として注目が高まっている。今回の新たな調達により、クラウド処理やAI学習環境を強化し、量産車向けの実装を視野に入れる。
ソフトバンクグループはAI関連投資を加速させており、傘下のアームを通じたAI半導体戦略に続き、自動運転やロボティクス分野にも本格展開する姿勢を明確にしている。マイクロソフトとの共同出資は、クラウドとAIチップ、エッジ制御を一体化する構想の一環とみられる。
ABBは「電動化」「自動化」「ロボティクス」を中核とする産業技術のグローバル企業で、今回の売却はエレクトリフィケーションとオートメーション領域に経営資源を集中させる狙いがある。ソフトバンクグループは「AIロボット事業を飛躍的に強化する」とコメント。孫正義会長兼社長は「ASI(人工超知能)とロボティクスを融合させることで、人類の未来を切り拓く段階的な進化を実現する」と述べた。
同社は併せて、ロボティクス関連投資を一元管理する中間持株会社を設立。ソフトバンクグループ本体から13社、傘下のビジョン・ファンドから27社の出資先を移管し、相乗効果の最大化と企業価値向上を狙う体制を整えた。これにより、産業ロボット、物流自動化、サービスロボットなど多岐にわたる事業ポートフォリオを統合し、AI技術を中核とした総合ロボティクス企業群を形成する。
2025年6月期(第1四半期)決算では、売上高1兆8203億円、経常利益6899億円、当期利益4218億円を計上。前年同期の赤字から黒字転換し、AI関連銘柄やテクノロジー投資先の再評価益が寄与した。2026年3月期通期では、売上高7兆4000億円、経常利益1兆円、当期利益5400億円を計画する。1株利益は379.08円、配当は年22円を予定しており、前期比で安定的な株主還元を維持する見通しだ。
みずほ証券は今回のレポートで、1.アーム株高を背景としたNAV押し上げ効果、2.ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)の評価益回復、3.財務体質改善とリスクプレミアム縮小を主な根拠に挙げたとみられる。特に、AI・データセンター向け半導体の中長期需要拡大を背景に、グループ全体の資産価値向上が進むと分析している。
市場では、ソフトバンクGを「AIエコシステムの中核投資持株会社」と位置づける見方が広がりつつある。AI関連株のボラティリティに注意が必要なものの、テーマ性の強さと保有資産の上振れ期待を背景に、みずほが掲げた2万8000円は中期レンジの上限に位置する。
同社はこれまで、世界各地のスタートアップに分散していたロボティクス関連の出資先20社をグループ内で統合。AI技術の進化を背景に、ソフトウエア、センサー、通信など各社の技術を横断的に連携させ、事業の効率化と成長加速を図る。ソフトバンクの孫正義会長はかねて「人型ロボットとAIの融合が次の産業革命を生む」と語っており、今回の組織再編はその構想の実現に向けた布石といえる。
2026年3月期第1四半期(2025年4〜6月)の連結決算は、売上高1兆8,203億円(前年同期比7%増)、税引前利益6,899億円と大幅な増益となった。ビジョン・ファンド事業がAI関連銘柄の上昇で黒字転換し、親会社株主に帰属する純利益は4218億円と前年の赤字から黒字に転じた。
市場では、AIとロボット事業を一体運営することで、SBG株が最高値圏で推移する中、さらに成長期待が高まるとの見方が出ている。同社がAIインフラ投資とロボティクスを両輪とする戦略を明確に打ち出した点は、長期的な株価押上げ要因になると評価したい。
もっとも、アームとクアルコムはライセンス契約を巡り係争中であり、収益化の速度や規模は不透明な側面を残す。加えて、クアルコムは設計を内製化する動きもみせており、アームへの依存度が将来的に低下する可能性もある。市場では「収益押し上げ効果を定量化するのは難しい」との指摘もある。
それでも、アームがAI向けCPUアーキテクチャで優位性を確立できれば、ソフトバンクGにとっては保有資産価値の上昇要因となる。特に同社はアーム株の上場益を原資に投資活動を展開しており、V9採用の広がりは資本効率改善や投資余力の拡大につながりうる。クアルコムとの関係性は複雑だが、アームの技術基盤が業界標準として浸透することは、ソフトバンクGの企業価値を高める方向に働くと見られる。
注目すべきは、ソフトバンクが追加出資に動いた時点でオープンAIがすでに「時価総額3000億ドル企業」として評価されていた点である。これは従来のスタートアップ投資と異なり、成熟した超大型の未上場企業に巨額の資金を投じる戦略であり、AI革命を「インターネット登場以来の構造変革」と捉える市場の見方を反映している。
オープンAIが依然として非上場であるなか、ソフトバンクグループは代替的な投資先として投資家の注目を集めている。ビジョンファンドを通じてAI関連企業への投資実績を積み上げ、今回の巨額出資によってオープンAIの成長を間接的に取り込むポジションを確立した。こうした背景から、同社株はAI関連ニュースや評価額の変動に敏感に反応する傾向が強い。
投資家にとってソフトバンクグループは、オープンAI本体の株式公開を待たずに、その企業価値上昇とAI産業の爆発的拡大を先取りできる戦略的な銘柄として存在感を高めている。
ソフトバンクは過去にもOpenAIに対し大規模な出資を行ってきた。2025年3月には、最大400億ドルの追加出資枠を確保する契約を締結。その直前の資金調達ラウンドでは、OpenAIの評価額は3,000億ドル規模とされ、ソフトバンクはその大半を担う投資家として関与した。初期段階ではセカンダリー市場を通じて数億ドル規模の株式取得も実施しており、段階的に出資を拡大してきた経緯がある。今回の評価額上昇は、過去の投資判断が資産価値の押し上げにつながった可能性を示すものだ。
一方で、国内における共同事業の立ち上げは遅れているとの観測もあり、グローバルでの積極投資と国内展開のギャップが課題とされる。投資規模の拡大はソフトバンクの財務余力を試す局面でもある。
直近の2025年3月期連結決算は、売上高約7兆2,000億円、最終損益は1兆1,500億円の黒字を計上した。営業利益の詳細は開示されていないが、投資収益の改善が寄与した。今期通期予想については会社発表で「非開示」とされており、AI投資の収益化は依然として見通しに不透明感が残る。ただし市場では、OpenAI関連事業を含むAI分野が成長ドライバーとなり得るとの期待が強い。
株主還元については、自社株買いや配当の継続に加え、資産売却を通じた資金確保で投資と還元の両立を目指す姿勢を維持している。今後は、OpenAI投資の成果をどのように利益へと結び付けるかが最大の焦点となる。評価上昇という追い風を享受しつつ、過去の投資で露呈したリスク管理の課題をどう克服するかが、投資家から問われている。
テザーは米ドルに連動するステーブルコイン「USDT」を発行しており、市場流通額は約1,100億ドルに達している。今回の私募では企業価値を最大5,000億ドル(約74兆7,600億円)と評価し、約3%の株式と引き換えに150億〜200億ドルの資金調達を目指すとみられる。
実現すれば、テザーは非上場企業として世界でも有数の高い評価額を獲得することになる。ソフトバンクGはこれまでAI基盤やデータセンターなど成長分野への投資を拡大しており、暗号資産分野への関与が加速する可能性もある。アークは成長企業への積極的な運用で知られており、両社の動向はデジタル金融市場全体に波及効果を及ぼすとみられる。
孫氏は10年以内にASIが人類知能を大幅に凌駕し、新たな産業構造を形成すると予測する。その結果、世界GDPの5%相当となる600兆円規模の収益がAI関連で生まれ、その果実を握るプラットフォーマーが数社に集約されるとみる。ソフトバンクGは「その1社になる」ことを目指す姿勢を鮮明にした。
この戦略を裏付けるのが、ソフトバンクGが進めてきたAI関連投資だ。中核を担うのが、英半導体設計会社Armと米OpenAIである。Armは2016年に買収し、現在はスマートフォンから自動車まで幅広い分野にチップ設計が採用されている。高性能かつ省電力な設計はAI時代の基盤技術と位置付けられ、孫氏は「今後のAI社会を支える要」と強調している。
一方のOpenAIはChatGPTを代表とする生成AIの旗手であり、ソフトバンクGは数兆円規模の出資を決断した。孫氏は「将来、地球上で最も価値ある企業となる」と語り、かつてアリババに投資した成功体験になぞらえている。
加えて、ソフトバンクGは米国での大規模AIインフラ構想「スターゲート」に参画し、OpenAIや米オラクルと共に数兆ドル規模のデータセンター網を構築しようとしている。世界最大級の計算基盤を整備し、AIモデルの進化に不可欠なリソースを押さえる狙いだ。ソフトバンクGはAI関連投資を軸にポートフォリオを組み替え、次の成長ステージに踏み出している。
孫氏が描く「AI収益600兆円構想」は、単なる夢想ではなく、ArmとOpenAIを両輪とする現実的な布石に支えられている。今後10年でASI時代が到来するとの前提に立ち、ソフトバンクGは再び世界市場を揺るがす存在となる可能性を秘めている。
OpenAIは、今回の拡張が2025年末までに掲げる「5000億ドル規模・10GW」のコミットメント達成に向け大きな前進であると強調した。生成AIの普及に伴い演算能力需要が急拡大する中、Stargateは次世代AIモデルの開発と商用化を支える中核インフラとなる位置づけだ。
ソフトバンクGにとっても、AIインフラ事業の拡大はビジョン・ファンド戦略の中核を強化するものであり、通信からAIプラットフォーム企業への転換を加速させる狙いがある。今後は米国内での拡張だけでなく、日本やアジア地域への展開可能性も注目される。
テキサス州アビリーンにある旗艦拠点やCoreWeaveと進行中のプロジェクトを合わせると、スターゲートは7GW近くの計画容量と今後3年間で4000億ドルを超える投資規模に達する。これにより、2025年1月に発表した総額5000億ドル・10GWのコミットメントについて、2025年末までに達成する見通しが立ったとしている。
ソフトバンクグループの株価は+5.97%の19000円で推移している。
OracleはOpenAIとの契約で年3,000億ドル(4兆円強)規模。これはクラウドの直接ホスティング契約であり、SaaSインフラ収益の典型。
・ソフトバンクの立ち位置
通信・データセンター投資、Armの半導体エコシステム展開、AIサーバー調達・提供などを担う可能性が高い。インフラ投資家としてのリターンは「使用料・持分利益・配当」に帰着。
・収益シェアの試算
スターゲート計画総額5,000億ドルを4年=年1,250億ドル規模の投資。Oracleが3,000億ドル規模を握るなら、ソフトバンクは「ArmのIP+AIデータセンター運営」で全体の10〜20%のキャッシュフローシェアを取るシナリオが妥当。年間ベースで125〜250億ドル(約1.8〜3.6兆円)規模の収益機会。
・最終利益への落とし込み
ソフトバンクの事業特性上、投資額に対して高マージンは取りにくい(データセンター運営や回線事業は20〜30%程度)。仮にEBITマージン25%とすれば、年間最終利益で4,000〜9,000億円規模の上積みが見込める。
「スターゲート計画」が予定通り進み、ソフトバンクがAIデータセンターやArmの半導体エコシステムを主導的に取り込んだ場合、年間最終利益で4,000億円〜9,000億円規模の寄与が現実的なレンジと考えられる。これは現在のソフトバンクグループの純利益水準(1兆円前後)に対して大幅な上積みとなり、企業価値の再評価余地は極めて大きい。
クラウド契約に準じた分配割合やOpenAI事業売上の成長率、競合企業のロイヤリティ水準を考慮すれば、数千億円から兆円規模の利益寄与が期待される。今後4年間のAIインフラ市場拡大とOpenAI関連の売上成長にリンクして、ソフトバンクグループの持分利益が大きく上振れる可能性が高い。ソフトバンクの将来利益は総額で1000-2000億ドル規模(約14-28兆円)と想定する向きもある。
米国政府もまたインテルへの資本注入を行う計画・実施中である。インテルの株式を 約10% 保有する方向で交渉中、また一部の助成金/補助金を株式取得の形で換える動きも含まれる。
エヌビディアはインテルに対し 50億ドル を出資する。出資は新株を取得する形式で、取得価格は1株あたり 23.28ドル。この出資後の保有比率は 約4%。
ソフトバンクが1株23ドルで取得したインテル株が、 株価 30ドル前後 で取引されていると、含み益率はおよそ 30〜40% 程度になる可能性がある。ソフトバンクグループはインテル株の投資で、現時点でおよそ 1000億円弱の含み益 を抱えている計算になる。
2025/09/16 岩井コスモ A継続 16,000 → 21,000
2025/09/04 SBI 買い継続 15,000 → 18,000
2025/08/28 大和 2継続 8,770 → 17,220
2025/08/27 SMBC日興 1継続 11,000 → 20,000
2025/08/22 野村 Buy継続 14,120 → 16,450
2025/08/15 ドイツ Buy継続 14,250 → 20,000
なかでも突出するのがソフトバンクグループ(9984)だ。同社は米オープンAIなどと共同で、米国における総額5000億ドル(約74兆円)のDC建設投資計画を発表した。単独企業グループとしては世界最大級であり、他の米大手を圧倒する規模となっている。背景には、AIによるデータトラフィックの急拡大とGPU需要の爆発的増加がある。
巨額投資の一方で、電力不足は業界共通の課題だ。膨大な電力を消費するDCの稼働には、再生可能エネルギーだけでは賄い切れず、原子力発電の活用が再評価されている。また将来的には核融合発電の実用化を視野に、長期的な電力購入契約(PPA)を結ぶ動きも広がっている。AI時代のインフラ競争は投資規模だけでなく、電力確保戦略でも熾烈さを増している。
なかでも突出するのがソフトバンクグループ(9984)だ。同社は米オープンAIなどと共同で、米国における総額5000億ドル(約74兆円)のDC建設投資計画を発表した。単独企業グループとしては世界最大級であり、他の米大手を圧倒する規模となっている。背景には、AIによるデータトラフィックの急拡大とGPU需要の爆発的増加がある。
巨額投資の一方で、電力不足は業界共通の課題だ。膨大な電力を消費するDCの稼働には、再生可能エネルギーだけでは賄い切れず、原子力発電の活用が再評価されている。また将来的には核融合発電の実用化を視野に、長期的な電力購入契約(PPA)を結ぶ動きも広がっている。AI時代のインフラ競争は投資規模だけでなく、電力確保戦略でも熾烈さを増している。
ソフトバンクグループはAIインフラ需要の拡大を追い風に、投資先の企業価値上昇が連鎖的に波及する構図が意識されやすい。今回のオラクル株急騰は、グループが掲げるAIエコシステム構想の現実味を市場に印象づける効果を持つだろう。短期的にはオラクル急伸に連動する形で思惑買いが入りやすく、株価押し上げ要因となる見通しだ。
一方、ソフトバンクG本体の収益貢献は限定的との冷静な見方もあり、持続的な株価上昇には追加的な投資成果や資産売却による財務改善など具体的な材料が求められる。株価はこれまでNAV(純資産価値)に対して大幅なディスカウントが続いていたが、スターゲート関連の実需顕在化により、投資家の見方が変化する局面に入った。短期的にはオラクル株急騰を材料に思惑的な買いが入りやすく、中期的には生成AI関連テーマの本格化で再度上値を試す展開が見込まれる。
(9984)ソフトバンクグループは、同社の主力投資ファンド「ビジョン・ファンド」を通じてレボリュートへ出資しているが、ソフトバンクが当初の出資持分を維持していた場合、理論上の含み益は数十倍規模に達する可能性がある。投資額800百万ドルに対し、評価額は約74倍の水準に拡大した計算だ。実際の持株比率や希薄化を踏まえると変動はあるが、ソフトバンクの投資戦略の中でも極めて成功した案件の一つと位置付けられる。
フィンテック関連テーマへの注目は続いており、レボリュートは世界的な事業拡大を進めている。ソフトバンクグループが保有するレボリュート株の評価益は、同社の決算や今後の株価動向にとっても重要な指標となり得る。
SVFの投資先企業の価値上昇や、AI関連スタートアップへの投資成果が市場の信頼を高め、株価のディスカウント是正(NAV割引の縮小)への期待を後押ししている。
ドイツ証券は、AI投資先の企業価値向上を積極的に評価し、ビジョンファンド経由での成長戦略が収益効率化に繋がると分析している。世界的なAIブームを背景にソフトバンクグループが主導する資本効率の高い投資活動を目標株価の上方修正要因とみている。
また、エヌビディア株を追加取得したことが明らかになり、市場で大きく注目された。この動きは、AI半導体需要の増大を背景に、ソフトバンクグループのポートフォリオ価値向上につながると見られる。
売却の背景には、米国で加速するデータセンター整備やAI(人工知能)関連インフラ投資の財源確保があるとみられる。ソフトバンクグループは生成AIを成長戦略の中核に据えており、半導体や次世代通信を含むエコシステム構築に資金を振り向ける方針を鮮明にしている。
特にデータセンター建設などインフラ整備には巨額の資金が必要であり、成長分野に資金をシフトする動きと受け止められる。今後も非中核資産の整理が進み、AI領域へと資本を一段と集中させる可能性が高い。
同社はかつてDRAM大手キングストンに出資したが、半導体市況の急変と価格競争で損失を抱え、撤退を余儀なくされた。その経験が尾を引き、ソフトバンクGは半導体メーカーへの直接投資を控えてきた経緯がある。その一方で、2016年には英Armを買収し、設計分野を重視する戦略へとシフトした。
今回のインテル出資は、AI需要拡大が半導体産業全体を押し上げる流れを見据えたものだ。インテルは最先端プロセスで台湾TSMCに後れを取っているが、先端GPU分野のNVIDIAやサーバー向けCPU市場で存在感を維持している。とりわけ自社工場を活用し、外部からの受託製造事業を拡大しており、ソフトバンクGのグローバルな投資ネットワークとも協調余地が生まれる可能性がある。
マーケットの評価は分かれる。ソフトバンクGはビジョンファンドを通じ、AI関連スタートアップ投資に注力しているが、直接的な半導体メーカー支援は異例で、収益化まで時間を要する可能性もある。それでも、生成AIブームで演算需要は増す一方であり、過去の失敗を糧にした再挑戦と捉える見方も強い。
今回の出資は、ソフトバンクGのAI領域における投資戦略を一段と鮮明にする動きであり、そこで得られるリターンがインテルの復活とともに市場で評価されるか否か、注目される。消化までは時間がかかる。
一方で、8月13日にはモルガン・スタンレーが「イコールウェイト」を継続し、目標株価を8000円から1万5000円へ設定。市場全体のAI関連バリュエーションの高まりを認めつつも、投資リスクを勘案し中立姿勢を維持した。12日には岩井コスモ証券が「A」を継続し、1万3000円から1万6000円への引き上げた。
さらに8日にはジェフリーズが「Hold」を継続し、目標株価を7780円から1万940円へ引き上げたものの、依然として中立評価を崩していない。
総じて、足元では強気評価が優勢であり、海外勢がAIやデータセンター投資拡大に伴う成長性を強調している。一方で、ソフトバンクグループの投資収益の変動性やマクロ環境の影響を指摘し、評価の温度差は残る。今後はArmの業績動向やAIインフラ投資「スターゲート」の具体化が株価に大きな影響を与える展開となりそうだ。
売却が実現した場合、オープンAIの企業価値は現行の3,000億ドルから一気に5,000億ドルへ上昇する見込みだ。これは、未上場グローバルスタートアップの中でも突出した水準であり、トヨタ自動車の時価総額を大きく凌駕する規模となる。
企業価値の算定方法は、今回のような株式譲渡取引における投資家間の合意額がベースとなり、従来の資金調達や売上高予測、成長性など事業評価も加味される。2024年のオープンAIの売上高は37億ドル、2025年には116億ドルと急拡大が予測されている。最新技術の投入や成長性が高い事業領域も評価額の上昇要因とされている。
ソフトバンクグループは2025年4月時点で最大400億ドルの出資を実施し、オープンAIの資金調達額は83億ドル、評価額は3,000億ドルに到達した。直近の自社株売却検討によって、評価額はさらに7割増を見込む。ソフトバンクGは今後もAI分野への積極投資姿勢を示しており、オープンAIの価値向上とともに同社のAI戦略への期待も膨らんでいる。
PayPayはソフトバンクグループ中核企業のソフトバンク株式会社およびLINEヤフー株式会社の子会社であり、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2の投資先でもある。PayPayは国内キャッシュレス決済市場で圧倒的なシェアを有しており、今後はグローバルな資本調達と事業展開が本格化する可能性が高い。
今回の動きは、(9984)ソフトバンクグループが掲げる投資回収戦略の一環と位置付けられ、将来的な資産価値向上とポートフォリオ強化を狙うものだ。ただし、本新規株式公開が実現してもPayPayは引き続きソフトバンクグループの連結子会社となる見込みであり、発表資料では現時点で連結業績や財政状態への重要な影響は想定していないとしているが、PayPayの米国上場は企業価値拡大や今後の資本政策に大きな転換点をもたらす。
新型CPUはカスタマイズ可能なベース設計を採用し、大手顧客の要望に合わせた仕様で提供される見込みで、製造はTSMCなど外部に委託する形式をとる。
今回の戦略転換の背景には、AIインフラ強化や半導体供給網の多様化をにらんだ事業モデルの再構築がある。AI向けデータセンター市場は急拡大しており、ARMが狙うASIC分野は2030年にかけて世界で約2,000億ドル規模に達すると見込まれる。
収益シミュレーションでは、同市場で7%のシェアを確保した場合、年間80〜150億ドル規模の売上が見込まれる。従来の顧客であるNvidiaやBroadcomなどとの関係再構築を伴う可能性はあるものの、自社ブランドでのAI半導体投入は、ARMの成長戦略における重要な転換点となる。
ここまでのソフトバンクグループの株価上昇は、出資先のオープンAIの評価増を織り込んだものだが、年末にかけてはARM株上昇が新たな株価上昇要因となる可能性がある。ARMはじっくりと時間をかけて、新型チップに資金を惜しみなく投入している。
構成の中核はArmで、19.83兆円と株式価値の約51%を占める。SVF2は5.86兆円、SBKKは3.47兆円。Armの価格感応度は高く、Armの時価が1%動くと持株価値が約0.21兆円、1株換算で約±148円動く計算だ。
財務運営面では「通常時LTV25%未満(非常時35%上限)、2年分以上の償還資金確保」が方針であり、現状の17%は許容範囲内に収まる。8月7日までの自己株取得は4,203万株・3,303億円で、需給の下支え要因となっている。
OpenAI評価のNAV寄与は、4月にOpenAIへ100億ドルを拠出し、年内条件充足で最大300億ドルまで積み増す枠組みだ。初回資金は事前評価2600億ドル基準で転換権を取得、ポストマネーでは概ね3.7%相当。仮にOpenAIのセカンダリー評価が5000億ドルで定着すれば、初回100億ドル分の含み益は約85億ドル、1株NAVで約+900円程度、最大300億ドルまで実行・同評価なら+2000円超の押上げ余地となる。評価が3000億ドル近辺にとどまれば押上げ幅は大きく低下する。
OpenAIの事業指標は加速しており、年売上は7月時点で約120億ドル、年末には200億ドル水準が見込まれる。一方で推定キャッシュバーンは年80億ドルに上方修正されたとの見方もあり、評価持続の鍵は収益化の速度とインフラコストの抑制だ。EV/売上でみると評価5000億ドルは年率120〜200億ドル前提で約25〜42倍のレンジとなり、感応度は極めて高い。
現在のOpenAI投資は未上場株の評価益としてNAVに反映されているが、IPOで市場価格が確定すれば、評価が会計上実現利益に転換する。特に5000億ドル評価水準で上場すれば、100億ドル出資時点の評価(約2600億ドル)との差分で大きな含み益が生まれる。今後数年はソフトバンクグループをホールドすべきと考える。
投資事業においては、NVIDIA株の評価益などが寄与し、ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)事業もクーパンやSymboticなど主要投資先の株価上昇によって大きく利益を押し上げた。税引前利益も6,899億円と、前年同期(2,256億円)から2.1倍以上の水準となった。
一方、Tモバイル株の売却益やアリババ株評価損が重しとなったが、為替差益やアリババ関連のデリバティブ益がこれを補い、グループ全体として損益の質が向上している。
今期は引き続きAI関連や海外通信株の資産入れ替え、中長期成長への積極投資を継続。市場予想を上回る高水準の四半期利益となったことで、事業ポートフォリオの進化と財務基盤への信頼感が広がる。
資産合計は44兆8417億円。なお、OpenAI Globalへの最大300億ドルの出資計画が進行しており、第1四半期には初回100億ドルを拠出。自己株式も引き続き取得しており、今期は3303億円分を実行した。
ソフトバンク1社で既に年4500億円規模の利用が見込まれることから、同様のスケールで他社が導入すれば、将来的には数兆円規模のビジネスに成長することも現実的だ。OpenAIが展開する企業向けAIサービスはすでにグローバルで急成長しており、今後のAGI(汎用人工知能)時代の中核インフラとして、業種横断的な普及が期待される。
このAIの強みは、企業の既存システムやデータと柔軟に連携し、個別最適な判断支援や業務改革を可能にする点にある。採用企業は、定型業務の自動化によるコスト削減、生産性の向上、データ統合による経営判断の高度化、さらには顧客満足度の向上や新規事業の創出といった多方面で恩恵を受ける。特に金融や通信、製造、小売、物流など、業務が複雑かつデータ量の多い業界での導入効果は大きい。先進AIの導入により、企業は競争優位を確立し、次世代のビジネスモデルを主導する存在となるだろう。
(8411)みずほフィナンシャルグループは、クリスタル・インテリジェンスを金融業界で初導入し、2030年度までに2024年度比で約3,000億円の業務効果を生み出す計画を発表した。具体的には、24時間365日顧客への最適サービス提供、営業生産性の2倍超向上、低付加価値業務の最大50%削減などを通じ、迅速な意思決定と新規ビジネス創出を支援する。
クリスタルインテリジェンスの将来的な売上規模を推測することは極めて困難だが、みずほが具体的な成果を打ち出したことで、他業種でも導入が進むのは間違いない。再び、ソフトバンクグループに夢を託すステージと思われる。
OpenAIへの出資額は過去分を含め約4.8兆円に達しており、孫氏は「OpenAIの売上高の急伸を踏まえ、あと数年で株式市場に上場できる」との見通しを示した。OpenAIは2025年の売上高を前年比3倍の127億ドル(約1.9兆円)と見込んでおり、対話型AI「ChatGPT」の有料サービスが成長を牽引している。孫氏は「OpenAIはいずれ上場し、将来的には地球上で最も価値ある企業になる」と自信を見せた。
今後もソフトバンクグループはAIインフラへの巨額投資を継続し、ASI時代の産業基盤の中核を担う戦略を鮮明にしている。グループのAI領域での攻勢とOpenAIの上場動向は今後の株価材料として注視すべきテーマだ。
この巨大プロジェクトは「プロジェクト・クリスタルランド」と呼ばれ、中国の深センに匹敵する製造拠点および産業複合施設の建設を目指している。複合施設にはAI搭載の産業用ロボットを製造する生産ラインが含まれ、主に高度技術製造業を米国に呼び戻すことを目的としており、これはトランプ政権の主要目標とも一致している。
孫氏はハワード・ラトニック商務長官を含む米国政府高官と潜在的な税制優遇措置について協議を進めており、サムスンなど他のテクノロジー企業にもこのプロジェクトへの参加を呼びかけているという。また、ソフトバンクグループのポートフォリオ企業もこのプロジェクトに関与させることを検討している。
同計画は、オープンAIが各国政府と連携しAIインフラを整備する「OpenAI for Countries」構想の第1弾であり、初期段階では1GW規模のAIクラスター、そのうち200MW分が2026年中に稼働予定だ。最終的には5GW規模のデータセンター群となる計画で、電力は原子力や再生可能エネルギーなど多様なソースから供給される。
しかし、米国当局はUAEと中国の関係やAI半導体技術の海外流出リスクを強く警戒している。高性能半導体の輸出に必要な安全保障条件や湾岸諸国との合意執行方法が依然として確立されておらず、計画の進展はほとんど見られない。UAE側は米国の技術流出防止策や国家安全保障規制の導入に合意したものの、米政府内ではその実効性に疑問の声が根強い。
ソフトバンクグループにとっては、AIインフラ分野での国際協調の象徴的プロジェクトだが、米国の安全保障政策が今後の進捗を大きく左右する見通しだ
この出資契約には、オープンAIが2025年内に営利企業(PBC)へ移行しなかった場合、ソフトバンクグループが出資額を400億ドルから200億ドルに半減できる条項が盛り込まれていた。営利企業化は、AI開発資金の調達を容易にし、投資家リターンを明確化する目的があったが、創業メンバーやAI研究者の反発を受け、オープンAIは営利企業化を断念したと発表した。
この方針転換により、ソフトバンクグループの出資額は最大で200億ドル減額される可能性が生じている。AI開発の資金調達力低下や、Stargateプロジェクトを含むAIインフラ投資計画の見直し、さらにNAV成長期待の修正が避けられない。今後、オープンAIの非営利体制維持による公共性重視のAI開発と、ソフトバンクグループのリターン最大化戦略のバランスが、引き続き注目される展開となるだろう。
ソフトバンクは、AI分野での成長を加速させるためOpenAIを重要なパートナーと位置づけており、今回の投資はその戦略の一環だ。しかし、この巨額投資により、同社の主要財務指標であるローン・トゥ・バリュー(LTV)比率が上昇し、2024年12月末時点で約21%だった水準から30%程度に達する可能性があるとS&Pは予測している。この水準は格下げ検討の目安とされる。
また、ソフトバンクは2025年1月に対米インフラ投資として約78兆円規模の計画を発表しており、3月には米アンペア社買収に約9,700億円を投じるなど、積極的な成長戦略を展開している。これらの動きが重なることで財務負担が増大し、迅速な資産売却や緩和策が求められる状況だ。
S&Pはソフトバンクの財務運営を「アグレッシブ」と評価しながらも、これまで一定の財務規律を維持してきた実績を認めている。しかし、今回の投資を含む急速な成長戦略が進む中で、適切な対応が取られない場合には格付け引き下げの可能性が高まると警鐘を鳴らしている。
(9984)ソフトバンクグループ(SBG)が、米国全土に人工知能(AI)を活用した工場群を集積する産業団地の構築を検討していることが明らかになった。この計画では、1兆ドル(約150兆円)を超える巨額の投資が見込まれており、労働力不足に直面する米国製造業への革新的な解決策として注目されている。今回の投資額は、1月に発表された5000億ドル規模のAIインフラ整備計画を大幅に上回るものとなる。
孫正義会長率いるソフトバンクグループは、AI搭載ロボットが自律的に稼働する工場群を目指しており、これにより製造業の効率化と労働力不足問題への対応を図る。AIを搭載したロボットは、人手が不足する分野において代替労働力としての役割を果たすと期待されている。自動化技術が進展する中、AI工場団地が完成すれば、製造コストの削減や生産性の向上が期待される。
孫会長は近々米国を訪問し、この産業団地構想について米政権と協議する予定だ。これにより、AIとロボティクス分野におけるソフトバンクの存在感がさらに強化される見込みだ。この計画は、テクノロジー業界のみならず、米国経済全体にも大きな影響を与える可能性がある。
アンペアは、エネルギー効率の高いAI向け半導体の設計を手掛けている。同社はArmのコンピュート・プラットフォームを基盤とし、高性能かつエネルギー効率に優れた持続可能なAIコンピューティング向け半導体設計を行っている。
ソフトバンクGは、クリスタル・インテリジェンスやスターゲートなどへの投資を通じてAIインフラ分野での投資を拡大しており、アンペアの買収によりこの分野をさらに強化できる。アンペアの買収により、ソフトバンクG傘下の英半導体設計大手アームとの連携が可能となる。これにより、生成AIで重要な役割を担う半導体の開発を加速させることができる。
アンペアは約1000人の優れた半導体エンジニアと技術開発力を有しており、アームの設計力を補完する形でArmベースのチップ開発を統合する模様。
アームは今後10年間にわたり、マレーシアに半導体の設計技術を提供することで合意した。この契約により、マレーシアは半導体産業の付加価値を高め、組み立て(パッケージング)から半導体製造へと事業領域を拡大する狙いだ。
マレーシア政府は、アームに対して10年間で2億5000万ドル(約375億円)を支払う。この投資は、半導体関連のライセンスやノウハウ取得の対価として位置付けられている。現在、マレーシアは世界の半導体パッケージングの約1割を担っている。今回の契約を通じて、より高付加価値な半導体製造への移行を目指している。
アームにとって、この契約はアジア市場での影響力拡大と新たな収益源の確保につながる。同社は2025年に内製半導体の市場投入を計画しており、マレーシアでの事業展開はその戦略と合致している。
報道によれば、この資金はAI技術の開発や関連インフラへの投資に充てられる見込みで、米国のオープンAIとの協業や「スターゲート」プロジェクトへの関与も背景にある。市場ではAIブームが続いており、ソフトバンクグループの財務戦略における攻めの姿勢を明確に示している。同社の戦略は成長期待を高める一方で、資金調達リスクへの警戒感も生んでいる。
この状況下での巨額借り入れは、AI分野でのシェア拡大を狙う大胆な賭けだ。成功すれば、成長期待から株価上昇が見込まれるが、負債総額の増加と金利負担が財務を圧迫するリスクは無視できないとして、短期的には強弱感が対立する。
https://www.asset-alive.com/thema/?mode=show&tid=9984
イーフィッシャリーは、養殖業者向けのスマート給餌システムを提供し、成長が期待される水産市場で注目されていた。2023年にはシリーズDラウンドで約1億ドルを調達し、ソフトバンクグループをはじめとする投資家が出資していた。しかし、経営の実態調査が進むにつれ、財務の健全性に対する疑念が浮上。現在、投資家の間では損失の最小化に向けた対応が急務となっている。
同社は、事業拡大のために積極的な投資を続けてきたが、市場環境の悪化や運営コストの増大が経営を圧迫したとみられる。調査結果を受け、今後は事業の再建計画や資金繰りの見直しが焦点となる。
https://www.asset-alive.com/thema/?mode=show&tid=9984