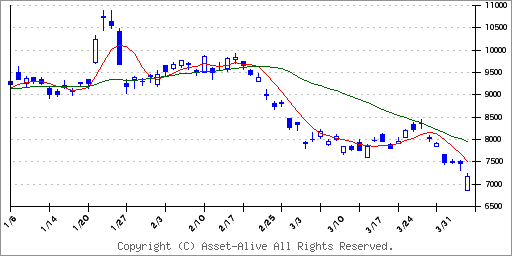注目銘柄
 2025/9/19 08:33
2025/9/19 08:33
(9984) ソフトバンクグループ 想定収益モデル
・Oracle事例の比較
OracleはOpenAIとの契約で年3,000億ドル(4兆円強)規模。これはクラウドの直接ホスティング契約であり、SaaSインフラ収益の典型。
・ソフトバンクの立ち位置
通信・データセンター投資、Armの半導体エコシステム展開、AIサーバー調達・提供などを担う可能性が高い。インフラ投資家としてのリターンは「使用料・持分利益・配当」に帰着。
・収益シェアの試算
スターゲート計画総額5,000億ドルを4年=年1,250億ドル規模の投資。Oracleが3,000億ドル規模を握るなら、ソフトバンクは「ArmのIP+AIデータセンター運営」で全体の10〜20%のキャッシュフローシェアを取るシナリオが妥当。年間ベースで125〜250億ドル(約1.8〜3.6兆円)規模の収益機会。
・最終利益への落とし込み
ソフトバンクの事業特性上、投資額に対して高マージンは取りにくい(データセンター運営や回線事業は20〜30%程度)。仮にEBITマージン25%とすれば、年間最終利益で4,000〜9,000億円規模の上積みが見込める。
「スターゲート計画」が予定通り進み、ソフトバンクがAIデータセンターやArmの半導体エコシステムを主導的に取り込んだ場合、年間最終利益で4,000億円〜9,000億円規模の寄与が現実的なレンジと考えられる。これは現在のソフトバンクグループの純利益水準(1兆円前後)に対して大幅な上積みとなり、企業価値の再評価余地は極めて大きい。
クラウド契約に準じた分配割合やOpenAI事業売上の成長率、競合企業のロイヤリティ水準を考慮すれば、数千億円から兆円規模の利益寄与が期待される。今後4年間のAIインフラ市場拡大とOpenAI関連の売上成長にリンクして、ソフトバンクグループの持分利益が大きく上振れる可能性が高い。ソフトバンクの将来利益は総額で1000-2000億ドル規模(約14-28兆円)と想定する向きもある。
OracleはOpenAIとの契約で年3,000億ドル(4兆円強)規模。これはクラウドの直接ホスティング契約であり、SaaSインフラ収益の典型。
・ソフトバンクの立ち位置
通信・データセンター投資、Armの半導体エコシステム展開、AIサーバー調達・提供などを担う可能性が高い。インフラ投資家としてのリターンは「使用料・持分利益・配当」に帰着。
・収益シェアの試算
スターゲート計画総額5,000億ドルを4年=年1,250億ドル規模の投資。Oracleが3,000億ドル規模を握るなら、ソフトバンクは「ArmのIP+AIデータセンター運営」で全体の10〜20%のキャッシュフローシェアを取るシナリオが妥当。年間ベースで125〜250億ドル(約1.8〜3.6兆円)規模の収益機会。
・最終利益への落とし込み
ソフトバンクの事業特性上、投資額に対して高マージンは取りにくい(データセンター運営や回線事業は20〜30%程度)。仮にEBITマージン25%とすれば、年間最終利益で4,000〜9,000億円規模の上積みが見込める。
「スターゲート計画」が予定通り進み、ソフトバンクがAIデータセンターやArmの半導体エコシステムを主導的に取り込んだ場合、年間最終利益で4,000億円〜9,000億円規模の寄与が現実的なレンジと考えられる。これは現在のソフトバンクグループの純利益水準(1兆円前後)に対して大幅な上積みとなり、企業価値の再評価余地は極めて大きい。
クラウド契約に準じた分配割合やOpenAI事業売上の成長率、競合企業のロイヤリティ水準を考慮すれば、数千億円から兆円規模の利益寄与が期待される。今後4年間のAIインフラ市場拡大とOpenAI関連の売上成長にリンクして、ソフトバンクグループの持分利益が大きく上振れる可能性が高い。ソフトバンクの将来利益は総額で1000-2000億ドル規模(約14-28兆円)と想定する向きもある。