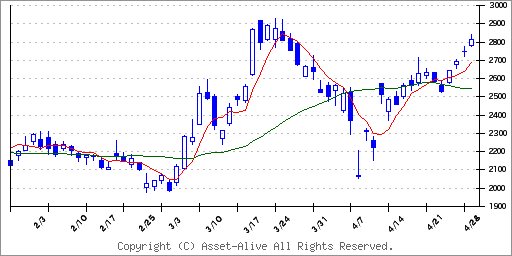注目銘柄
 2025/6/10 08:21
2025/6/10 08:21
NATO加盟国は2025年の首脳会議で、防衛費のGDP比目標を現行の2%から最大5%へ引き上げる方針で大筋合意した。この動きは日本の防衛政策にも影響を与えている。日本政府はNATOの要請を踏まえ、2027年度までに防衛関係費をGDP比2%(年間約11兆円)に増やす計画を決定した。これは従来計画の2倍以上の規模であり、防衛産業各社の売上は明確な上昇傾向にある。
長年「儲からない産業」と呼ばれた防衛ビジネスだが、ここ数年で状況が一変している。防衛装備庁が発注時の利益算定方式を見直し、企業に最大15%の利益を認める制度へ変更したこともあり、収益性が大幅に改善した。防衛省から直接受注する三菱重工業、川崎重工業、IHIの大手3社(いわゆる「プライム企業」)も、防衛関連事業が軒並み好転している。
三菱重工業は総合重機最大手として戦闘機、水上艦艇、潜水艦、艦載・水中機器、地対空誘導弾システム、空対艦誘導弾など幅広い防衛装備品を手掛ける。政府の2023〜27年度「防衛力整備計画」による防衛費拡大や「抜本的な防衛力強化」の方針の下、同社は需要増と採算性の向上が見込めるとしている。
実際、2024年度の航空・防衛・宇宙セグメント事業利益は前期比272億円増の999億円に達し、利益率改善が鮮明だ。三菱重工と防衛省との契約額は年間1兆円規模とされ、防衛関連事業の利益率向上が同社株価を押し上げる主因だ。同社株は2024年から2025年にかけて5倍超に急騰し、投資家は防衛事業の成長性に熱い視線を注いでいる。
防衛装備の開発・統合を担うプライム企業の筆頭である三菱重工は、国内防衛費拡大の恩恵を最も受ける立場にある。現在の株価水準を見ると、三菱重工は約3,455円(PER約44倍、PBR約4.9倍)と、川重の約10,645円(PER約21倍、PBR約2.5倍)、IHIの約15,560円(PER約20倍、PBR約4.9倍)に比べ割高感も指摘される。
ただし三菱重工は防衛事業の利益拡大余地が大きく、中長期的な成長期待が突出しているとの見方が強い。巨額の国家予算を背景に受注増と収益性向上が続けば、依然として同社株は有望な防衛関連株の筆頭と言えるだろう。
長年「儲からない産業」と呼ばれた防衛ビジネスだが、ここ数年で状況が一変している。防衛装備庁が発注時の利益算定方式を見直し、企業に最大15%の利益を認める制度へ変更したこともあり、収益性が大幅に改善した。防衛省から直接受注する三菱重工業、川崎重工業、IHIの大手3社(いわゆる「プライム企業」)も、防衛関連事業が軒並み好転している。
三菱重工業は総合重機最大手として戦闘機、水上艦艇、潜水艦、艦載・水中機器、地対空誘導弾システム、空対艦誘導弾など幅広い防衛装備品を手掛ける。政府の2023〜27年度「防衛力整備計画」による防衛費拡大や「抜本的な防衛力強化」の方針の下、同社は需要増と採算性の向上が見込めるとしている。
実際、2024年度の航空・防衛・宇宙セグメント事業利益は前期比272億円増の999億円に達し、利益率改善が鮮明だ。三菱重工と防衛省との契約額は年間1兆円規模とされ、防衛関連事業の利益率向上が同社株価を押し上げる主因だ。同社株は2024年から2025年にかけて5倍超に急騰し、投資家は防衛事業の成長性に熱い視線を注いでいる。
防衛装備の開発・統合を担うプライム企業の筆頭である三菱重工は、国内防衛費拡大の恩恵を最も受ける立場にある。現在の株価水準を見ると、三菱重工は約3,455円(PER約44倍、PBR約4.9倍)と、川重の約10,645円(PER約21倍、PBR約2.5倍)、IHIの約15,560円(PER約20倍、PBR約4.9倍)に比べ割高感も指摘される。
ただし三菱重工は防衛事業の利益拡大余地が大きく、中長期的な成長期待が突出しているとの見方が強い。巨額の国家予算を背景に受注増と収益性向上が続けば、依然として同社株は有望な防衛関連株の筆頭と言えるだろう。