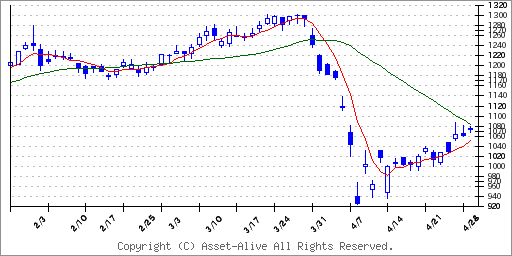注目銘柄
 2025/10/30 11:53
2025/10/30 11:53
(5471) 大同特殊鋼 中間実績が予想を大きく上回る 配当方針もDOE導入で株主還元を明確化
大同特殊鋼が10月30日に発表した2026年3月期第2四半期(中間期、25年4〜9月)は、売上収益が2844億99百万円と5月時点の会社計画(2750億円)を約95億円上回り、営業利益も184億64百万円と同計画125億円を大きく突破した。磁石製品で中国の重希土類輸出規制を背景に需要が強く、自動車向けエンジンバルブなども想定超で伸びたことが効いた。為替が円安方向で推移したことに加え、経費圧縮を進めたことで、親会社株主に帰属する中間利益は129億37百万円と前年同期を6%上回った。
あわせて、これまで「未定」としていた26年3月期通期を売上収益5650億円、営業利益330億円、税引前利益345億円、最終利益235億円と開示した。前期実績(売上高5749億円、営業利益394億円)より一段低い水準を見込むのは、自動車・産機向けの数量低迷や販売価格の一部下落、固定費増を慎重に織り込んだためで、会社側は「数量変化に応じた生産体制の見直しと価格転嫁でマージン確保を続ける」としている。
特殊鋼鋼材は自動車向けで減量し減収減益だった一方、機能材料・磁性材料は前期の子会社清算費用がなくなり増益、自動車部品・産機部品は一時費用で減益とセグメント内で明暗が分かれた。中間期の好調を受けて配当も増額し、9月末中間配当は従来予想16円を22円に引き上げ、期末も27円を見込むことで年間49円(前期47円)に上積みする。
さらに26年3月期から株主還元方針を改定し、従来の「配当性向30%以上」に加えて、親会社所有者帰属持分を基礎にしたDOE(株主資本配当率)2.5%を下限指標として導入、自己株式取得もキャッシュ・アロケーションの進捗を見ながら検討する枠組みに改めた。原燃料は依然高止まりし、米国の通商・関税政策や中東情勢など外部環境の不確実性も残るが、磁石など“重希土フリー”製品へのシフトは続く見通しで、会社は24年に公表した「2026中計」を再設計し、26年度営業利益「400億円以上」をあらためて掲げた
株主への還元姿勢を明文化したことは中長期の株価にはプラスに働きやすく、足元では自己株式取得で株数が減っていることも1株利益の押し上げ要因となる。もっとも通期計画は前期比で減益シナリオを置き、鋼材数量もなお回復を見込んでいないため、投資スタンスとしては「配当増とDOE導入で下値は固めつつ、需要回復の手掛かり待ち」という構図になる。
配当方針の格上げ(年間49円、DOE2.5%導入)は評価でき、自己株式取得も選択肢に入ったことで株主還元ストーリーは明確になった。一方で、会社が開示した26/3期の営業利益330億円は前期比16%減と慎重で、自動車・産機向けの数量と販売価格がなお重い。株価が配当増を一巡して織り込んだ後は、①磁石など高付加価値品の伸びがどこまで続くか、②米国関税やエネルギー市況など外部環境の変動をどれだけ価格に転嫁できるか、③再設計した中計で示した「26年度営業利益400億円以上」へのトラックレコード、が次の材料になるとみる。
あわせて、これまで「未定」としていた26年3月期通期を売上収益5650億円、営業利益330億円、税引前利益345億円、最終利益235億円と開示した。前期実績(売上高5749億円、営業利益394億円)より一段低い水準を見込むのは、自動車・産機向けの数量低迷や販売価格の一部下落、固定費増を慎重に織り込んだためで、会社側は「数量変化に応じた生産体制の見直しと価格転嫁でマージン確保を続ける」としている。
特殊鋼鋼材は自動車向けで減量し減収減益だった一方、機能材料・磁性材料は前期の子会社清算費用がなくなり増益、自動車部品・産機部品は一時費用で減益とセグメント内で明暗が分かれた。中間期の好調を受けて配当も増額し、9月末中間配当は従来予想16円を22円に引き上げ、期末も27円を見込むことで年間49円(前期47円)に上積みする。
さらに26年3月期から株主還元方針を改定し、従来の「配当性向30%以上」に加えて、親会社所有者帰属持分を基礎にしたDOE(株主資本配当率)2.5%を下限指標として導入、自己株式取得もキャッシュ・アロケーションの進捗を見ながら検討する枠組みに改めた。原燃料は依然高止まりし、米国の通商・関税政策や中東情勢など外部環境の不確実性も残るが、磁石など“重希土フリー”製品へのシフトは続く見通しで、会社は24年に公表した「2026中計」を再設計し、26年度営業利益「400億円以上」をあらためて掲げた
株主への還元姿勢を明文化したことは中長期の株価にはプラスに働きやすく、足元では自己株式取得で株数が減っていることも1株利益の押し上げ要因となる。もっとも通期計画は前期比で減益シナリオを置き、鋼材数量もなお回復を見込んでいないため、投資スタンスとしては「配当増とDOE導入で下値は固めつつ、需要回復の手掛かり待ち」という構図になる。
配当方針の格上げ(年間49円、DOE2.5%導入)は評価でき、自己株式取得も選択肢に入ったことで株主還元ストーリーは明確になった。一方で、会社が開示した26/3期の営業利益330億円は前期比16%減と慎重で、自動車・産機向けの数量と販売価格がなお重い。株価が配当増を一巡して織り込んだ後は、①磁石など高付加価値品の伸びがどこまで続くか、②米国関税やエネルギー市況など外部環境の変動をどれだけ価格に転嫁できるか、③再設計した中計で示した「26年度営業利益400億円以上」へのトラックレコード、が次の材料になるとみる。