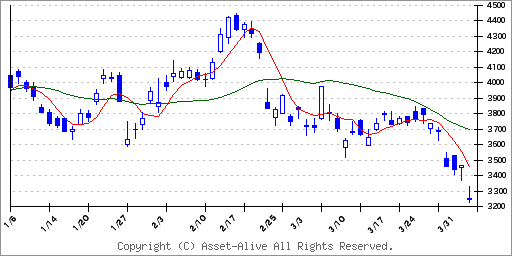注目銘柄
 2025/10/30 15:40
2025/10/30 15:40
6501日立製作所の2026年3月期第2四半期(25年4〜9月)連結決算は、売上収益が前年同期を上回り増収、調整後の営業利益も2ケタ台の増益となった。世界的に再生可能エネルギーを送電網に接続する需要が続き、北米・欧州で電力インフラ関連の大型案件が進んだことが大きい。国内ではデジタルシステム&サービス(DSS)が公共・金融向けを中心に堅調で、モダナイゼーション案件を着実に取り込んだ。結果として、全社の利益率は10%台に乗せてきた。
セグメントでは、エナジーが最も伸びが大きく、送配電や系統増強向けの高採算案件が利益を押し上げた。モビリティも欧州を中心に鉄道システム関連の需要が底堅く、過去に買収した事業の寄与が増えている。コネクティブインダストリーズは中国の昇降機や建機関連で需要の鈍さが見られるが、インダストリアル向けのサービスや半導体製造装置向けでカバーし、全体としては利益を維持した。DSSは海外ITで投資抑制の動きが出ているものの、国内の大型案件で人員を効率化し、採算を改善させている。
同時に会社は2026年3月期通期の見通しを上方修正し、売上収益を10兆円台前半に、調整後EBITAも前期を上回る水準に引き上げた。円安が海外事業の計上額を押し上げているほか、パワーグリッドを中心とした高利益の案件が期後半にも残っており、受注残の消化が通期を支える構図だ。純利益も従来計画より上振れさせ、キャッシュ・フローの改善を前提に自己株式の取得と配当の両立を示した。成長投資についても、Lumada関連のデジタル基盤への投下を続ける姿勢で、コア事業と非中核の入れ替えを進める。
リスク要因としては、中国の建設・不動産向け需要が引き続き低調であること、米国や欧州で保護主義的な関税が続く可能性があることが挙げられる。とくに素材・機器の一部でコスト上昇が残るほか、プロジェクト型のインフラ事業では採算管理を緩めにくい。日立は価格転嫁とプロジェクト選別で年度内の利益押し下げを一定範囲に抑える方針で、今期は「増収・増益・高水準CF」をそろえる計画だ。電力インフラとDXという成長分野を二本柱に据えた構成は変わらず、外部環境が揺れても売上のボリュームが確保しやすい体制になっている。
エナジーの受注残が厚く、通期の売上10兆円超と高めの利益率が視野に入っているうえ、自己株取得を含む株主還元が業績と連動している点は評価できる。一方で、中国関連の弱さや関税リスクが見通しを曇らせる場面も想定されるため、高値を一気に追うよりは、インフラ・デジタルの成長が確認できた押し目での買い下がりが現実的だと考える。中立〜やや強気としたい。
セグメントでは、エナジーが最も伸びが大きく、送配電や系統増強向けの高採算案件が利益を押し上げた。モビリティも欧州を中心に鉄道システム関連の需要が底堅く、過去に買収した事業の寄与が増えている。コネクティブインダストリーズは中国の昇降機や建機関連で需要の鈍さが見られるが、インダストリアル向けのサービスや半導体製造装置向けでカバーし、全体としては利益を維持した。DSSは海外ITで投資抑制の動きが出ているものの、国内の大型案件で人員を効率化し、採算を改善させている。
同時に会社は2026年3月期通期の見通しを上方修正し、売上収益を10兆円台前半に、調整後EBITAも前期を上回る水準に引き上げた。円安が海外事業の計上額を押し上げているほか、パワーグリッドを中心とした高利益の案件が期後半にも残っており、受注残の消化が通期を支える構図だ。純利益も従来計画より上振れさせ、キャッシュ・フローの改善を前提に自己株式の取得と配当の両立を示した。成長投資についても、Lumada関連のデジタル基盤への投下を続ける姿勢で、コア事業と非中核の入れ替えを進める。
リスク要因としては、中国の建設・不動産向け需要が引き続き低調であること、米国や欧州で保護主義的な関税が続く可能性があることが挙げられる。とくに素材・機器の一部でコスト上昇が残るほか、プロジェクト型のインフラ事業では採算管理を緩めにくい。日立は価格転嫁とプロジェクト選別で年度内の利益押し下げを一定範囲に抑える方針で、今期は「増収・増益・高水準CF」をそろえる計画だ。電力インフラとDXという成長分野を二本柱に据えた構成は変わらず、外部環境が揺れても売上のボリュームが確保しやすい体制になっている。
エナジーの受注残が厚く、通期の売上10兆円超と高めの利益率が視野に入っているうえ、自己株取得を含む株主還元が業績と連動している点は評価できる。一方で、中国関連の弱さや関税リスクが見通しを曇らせる場面も想定されるため、高値を一気に追うよりは、インフラ・デジタルの成長が確認できた押し目での買い下がりが現実的だと考える。中立〜やや強気としたい。